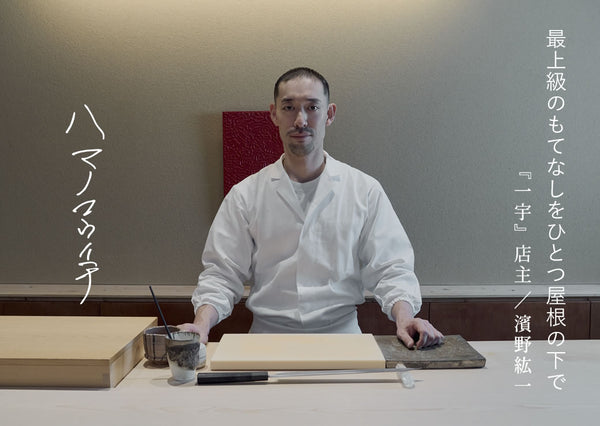ワインに人生を捧げる渋谷 康弘氏と語り合う、ワインと日本酒が創り出す文化

常識に囚われず、革新を起こし続けてきた一流たちのスピリットに触れるTAKANOME MAGAZINE。
今回話を聞いたのは、ワイン輸入商社株式会社グランクリュ・ワインカンパニーの代表を務めている渋谷 康弘氏。まだ日本にソムリエという言葉がなかった時代からフランスでワインを学び、帰国後インターコンチネンタルホテルズのチーフ・ソムリエに就任した。その後もシャネルと仏三つ星シェフ、アラン・デュカスが提携したレストラン「ベージュアラン・デュカス東京」の初代総支配人や「ピエール・ガニェール・ア・東京」など、多くの有名レストランの総支配人を歴任。ワイン文化に貢献しつづけている。今回はそんな渋谷氏と鷹ノ目代表の平野が、それぞれの専門分野であるワインと日本酒の魅力や、そこから生み出されている文化について語り合った。
なぜ数百万のワインが存在するのか。道なき道を行くワイン研究
鷹ノ目創業者 平野(以下 平野):ワインを仕事にしようと思ったのは、どうしてだったのでしょうか。
渋谷氏:きっかけは、当時日本で流行していたボジョレーヌーヴォーでした。勉強をしはじめたら、ワインには何十万円もするロマネコンティという種類もあるとわかりました。ボジョレーヌーヴォーのような大衆的なものと高級ワインではあまりにも値段が違います。その違いはどうして生まれるのか、知りたくなったんです。

インターネットがない時代でしたし、ワインに関する本などもほとんどありませんでした。なので百聞は一見にしかずだと思い、フランスまで行ってみようと思いました。
平野:ワインの勉強はどのようにされたのですか。
渋谷氏:当時は今のようにソムリエスクールなど、消費者用の勉強の場はなかったんです。教えてくれる人がいるとしたら、酒屋さんとかになります。なので色々な人に話を聞いたり、あとはとにかく有名な生産地を巡りました。パリに行き、ブルゴーニュ、イタリアにも行きました。
フランスにはワインの生産者に向けた学校があったので、そこに通うなどもしましたね。
平野:ソムリエという職業がなかったということは、その当時はワインを仕事につなげようとは考えていなかったんですか。
渋谷氏:僕は元々ホテルマンになろうと思っていたんです。観光について学んでいたし、英語やフランス語などの語学は必要なスキルでした。
でも丁度フランスで『ソムリエ』というものが登場し始めたんです。最初は有名なレストランでワインをつぐことが箔になりましたが、身につけた知識や自分の技量を競うコンテストが徐々に開催され始め、賞がプロモーションになりました。

帰国してから、フランスにいた時代に知り合った横浜のインターコンチネンタルの総支配人から、ソムリエにならないかと声を掛けていただきました。総支配人もマネージャーもフランス人だったので、ワインに詳しくて、フランス語と日本語ができる人材を求めていたんです。
先ほども言った通り日本ではまだまだソムリエって何? という時代ですから、日本人のスタッフには私が何をする人なのかわからなかったようです。
今はソムリエの資格を取るというのが当たり前だけれど、こういう歴史が積み重なって現在に繋がっています。
平野:ワインは生産者がいて、それをお客さんに伝えるソムリエさんがいるという流れがもはや文化を作っていますよね。
でも日本酒は、以前のフランスのようにまだまだ酒屋さんが紹介するくらいしかできていないのが現状です。この状態も、今後変えていけたらと思っています。
瞬間を味わう日本酒と、資産になるワイン。それぞれの魅力とは?
平野:お話を戻してしまいますが、なぜ数十万や数百万もするワインが存在するんですか。
渋谷さん:資産になるからだと思います。ワインは飲める状態が30年とか50年つづくんです。だからロマネコンティを持っていたとしても、みんな飲まないでしょう。資産としてとっておくんです。7000本しか作られないし、価値が下がらないから、将来の値段も担保されています。

元々ヨーロッパは、文化の価値を後世に繋いで行こうという意識が高いですよね。塩野七生さんの「わが友マキアヴェッリ」を読んで、ルネサンスに大きく貢献したイタリアの富豪であるメディチ家が「メディチが滅んでも、メディチがつくった文化は永遠に残る」という言葉を残していると知りました。この一節を見つけた時は、思わず感銘を受けましたね。スケールが大きいなと。
ワインはどれだけ価値と味を持続させるかが大切ですが、日本酒はその逆な気がします。四季折々の食材を楽しむみたいに、この瞬間しかこの味は飲めないんだ、ということがクールだと思われる時代が来るかもしれないですね。
平野:鷹ノ目もその日本酒ならではの魅力をまさに体現しています。心を込めて造り、絞ってから数日間寝かせ、全体の味わいをまとめてから、水曜日に注文を受け付けてから配送をしています。だからどこよりもフレッシュで、徹底した品質管理の元にお客様に配送し、ベストなタイミングで鷹ノ目を飲んでもらえるよう心がけています。
実は日本酒にも熟成酒というものがあったんです。でも第二次世界大戦の時に日本中が酒不足になり、熟成酒も飲んでしまったのでなくなってしまいました。その後からは作ってすぐ売る、という今の形が続いています。

そういった経緯も今の日本酒の文化を形成している大切な部分です。さらに、日本酒もワインのように熟成することで、味にしろそこから生まれる文化にしろ、さまざまな深みが生まれたら良いなと思います。
だから、僕らはフレッシュな新鮮さ以外にも、熟成させることで生まれる味わいに強く可能性を感じています。
鷹ノ目から感じた、ワインとは違った魅力
平野:最後に、ぜひ鷹ノ目を飲んでいただけたらと思います。
渋谷さん:花よりもフルーツのような香りが圧倒的に強いですね。メロンっぽい香りだと思いました。こういう香りはワインだとあまりないんです。

僕は味には持続性も大切だと思っているのですが、鷹ノ目にはそれもしっかりあります。舌に乗ってから、口の中に味が残る。
どこで作っているんですか。
平野:山口で作っています。お米も山口の山田錦です。山口のお酒は非常に人気が高まっており、国内のみならず、世界でも高い評価をうける日本酒が増えています。
渋谷さんが仰る通り、フルーツを感じさせる味なので、海外の方にも「おいしい」と感じてもらいやすいのだと思います。
ご感想、ありがとうございました。
 ▲渋谷 康弘氏 株式会社グランクリュ・ワインカンパニー代表取締役社長。ソムリエ・ワインクリエイター。80年代パリでワインを学び、帰国後インターコンチネンタルホテルズのチーフ・ソムリエとして多くのソムリエコンクールでも入賞を果たす。仏最高級ファッションブランド「シャネル」と、仏三つ星シェフ、アラン・デュカスが提携したレストラン「ベージュアラン・デュカス東京」の初代総支配人として開店に大きく貢献。仏三つ星シェフの東京店「ピエール・ガニェール・ア・東京」など多くの有名レストランの総支配人を歴任。2017年、ワイン輸入商社株式会社グランクリュ・ワインカンパニーを設立。完全会員制ワインクラブ「ザ・コンコルド・ワインクラブ」を運営。自らヨ-ロッパと北米のワイナリーを訪問しワインを買い付け、輸入業務を行う。NEW CITY CLUB OF TOKYOの開業時にワインセラーの総合監修を担当。
▲渋谷 康弘氏 株式会社グランクリュ・ワインカンパニー代表取締役社長。ソムリエ・ワインクリエイター。80年代パリでワインを学び、帰国後インターコンチネンタルホテルズのチーフ・ソムリエとして多くのソムリエコンクールでも入賞を果たす。仏最高級ファッションブランド「シャネル」と、仏三つ星シェフ、アラン・デュカスが提携したレストラン「ベージュアラン・デュカス東京」の初代総支配人として開店に大きく貢献。仏三つ星シェフの東京店「ピエール・ガニェール・ア・東京」など多くの有名レストランの総支配人を歴任。2017年、ワイン輸入商社株式会社グランクリュ・ワインカンパニーを設立。完全会員制ワインクラブ「ザ・コンコルド・ワインクラブ」を運営。自らヨ-ロッパと北米のワイナリーを訪問しワインを買い付け、輸入業務を行う。NEW CITY CLUB OF TOKYOの開業時にワインセラーの総合監修を担当。
TAKANOME(鷹ノ目)開発の背景

F1のレーシングカーを作るとき、コストを考えながら車を作ったりはしない。とにかく速さのみを求めてその時代の最高の車を作る。TAKANOME(鷹ノ目)の開発もいわばレーシングカーを作るかのようにとにかく「うまさ」のみを追求するとの信念のもと、幾度にも及ぶ試行錯誤の上で完成した、極上の日本酒。
<販売日>米作りからラベル貼りまで、全て「手作業」によって造っているため、生産量が限られています。ご迷惑をお掛けしますが、週に1度のみ(毎週水曜21時〜)数量限定で販売いたします。
飲む前に知って欲しい、鷹ノ目開発ストーリーはこちら
鷹ノ目の購入はこちら
Text: Megumi Saito
Photo: Hiroyuki Tamagawa
Structure: Sachika Nagakane